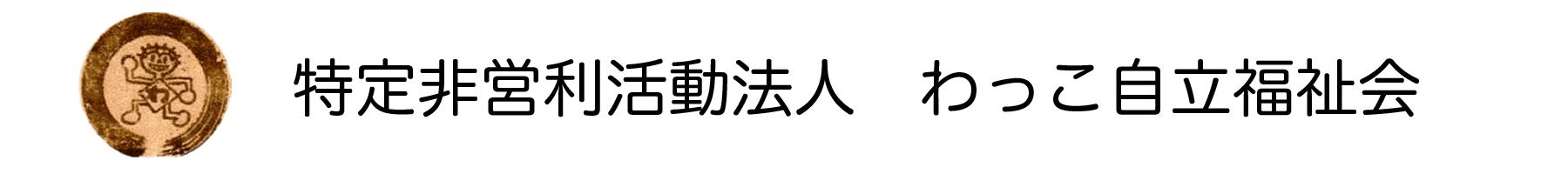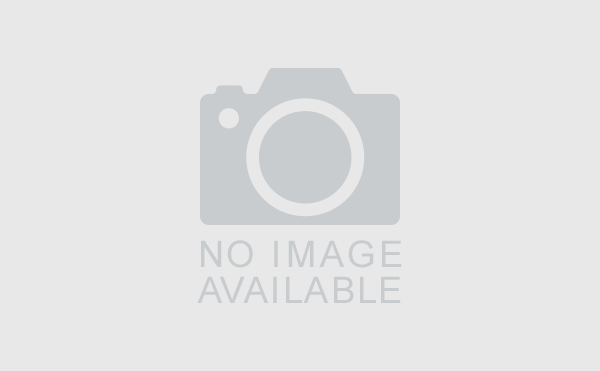【爺さんのたわごと】おかげさまで本をいっぱい読めました。
昨年の10月から骨折で入院し、退院したと思ったら今年の1月持病で入院、退院したと思ったら加齢で脊椎症と忙しく体は悲鳴を上げていますが、口だけは達者なので周囲に迷惑をかけて生きています。先日孫と夕食を食べたときに娘が葬儀用にと写真を撮り、いつ行ってもいいように準備をしておくと言ってくれてのびのびとその時まで生きていきます。
入院して久々の休暇をもらったので、読書三昧で暮らしました。何せ3食付きで、ご飯を作る心配もなく、片付ける心配もなく、何かというとナースは来るは、入浴は介助浴でご飯もおいしかったが、朝食は普段トースト1枚にサラダやチーズにコーヒーなのが、ご飯一式は食べきれなかった。
読書三昧をして大きく目を開かせてもらった本がいくつかある。
1,信州大学の教授本田秀雄の発達障害、知的障害シリーズだった。この本は入院中にどんな本をよんだらいいか知り合の障害者の女性に連絡をしたら、わざわざ病院まで本田秀雄の本と障害を持つ母親、難病障害者の自立に関係する書籍を届けてくれた(おやつも)。私などは70年代の障がい者運動の影響を深く受けて、青い芝だ自立生活運動だ、JLだ、DPIだと。最近はようやく頭がやわらかくなってきたが、本田秀雄の発達障害、知的障害の感性の豊かさに大きくこころを引かれた。私の中に知的障害をIQで判断していたところがあり、この人はこの部分でしか自立生活ができないのではないかと思いこむとところがあった。実はそれは単なる指標であって、行政が障害者手帳を作るときの判断でしかないこと。医学的には神経障害に入ること「「早く、ゆっくり」が支援ポイントであることや日本の障がい者施策が障がい者手帳によっていること。支援に合理的配慮」が必要なことなど。このシリーズの本を再度読み返している。
2,斎藤幸平の「ゼロからの資本論」シリーズ非常に現在を解き明かす著作だと思う。私たちの世代はマルク主義を権力論として解釈してきた世代だ。マルクスの問題意識は権力ではなく自然との共生をはかり、人間にとって必要な物質を共有することにあり、それが「コモン」。非常に面白い著書で、ロシアも、中国も国家資本主義の道を歩んでいるだけだ。アメリカの大統領になったトランプが典型的で不動産王で、周りにイーロン・マスクなどのIT起業家が集まって大企業集団としての政権を作っている。非常によくわかる。この人たちは何も生産をしていない。トランプは土地を転がし、IT起業家は人の情報を食い物にして世界を通信網で覆って、情報を提供することでお金を稼いでいる。9割の労働者がその食い物にされている。矛盾していることは資本が世界をかけめぐるグローバル化しているのに、「アメリカ第一主義」で一国主義を行うことの矛盾。この結末が見どころか。
3,信濃毎日新聞編集の満豪開拓団の記録(鍬を握るー長野県開拓団の記録)私の旧知に長野県満豪開拓団の教師として参加し砲弾で片目を失い3人の教え子と一緒に帰国し、その後千曲市で教員をしていた時の、最後の教え子の証言が信毎の特集に載っていた。知人だったので連絡を取り、本を依頼した。その知人も大病のなか活動を続けている。彼女は語ってくれたが、千曲市の満蒙開拓団ともつながっていることも分かった。歴史の中で苦闘し自問しながら生き続ける多くの人がいる。今再びそのような時代が訪れようとしているのか。
4,新たな時代に繋げられるのかと自分に問いかけている。友人で亡くなる者も増えている。道半ばで倒れる者もいる。産業廃棄物処理の闇を暴くために活動をしていた彼は、暴力団に脅迫され、家族へ危険がおよばないように別居生活をしながら活動していたが、がんで亡くなった。彼とは悪ガキでよく議論を交わした。その時私も病床で会えなかったことが今でも心残りになっている。
私たち(わっこ)が描いた介護保険制度が当初の理念と大きく変わってきている。介護保険制度を設立に向けて私たちも講演会を開たり、署名活動をもした。障害者の介護保障制度に繋がると期待が大きかった。介護保険制度が誰でもが使える制度ではなくお金がないと使えない制度に変遷し、且つ複雑化していった。介護難民が叫ばれている。介護事業所の倒産が相次いでいる。私どものところでも昨年、人員が確保できないため営業所を廃止した。職員の高齢化、担い手不足が深刻化している。保育の現場、医療の現場、教育の現場もそうであるように環境が悪すぎる。人の命や育ちに対する支援がなさすぎる。IT、軍備にはポンと何兆円もの税金を投資されている。企業が潤うだけで人の命や生活は潤わない。103万円の壁の議論はせこ過ぎる。教育費を無償化すれば済のではないか。安心して教育を受けられることが大切なのではないか。議論が間違っているように思う。
本題に戻ろう。介護保険制度と障害サービスの違いや、障害者が介護保険制度に移行するための「壁」が議論されている。その壁を緩くして国は、障害サービスを5年間利用していた障害者が介護保険に移行した場合、1割負担を償還払いで返金することや共生サービスの利用を進めている。一番大事な議論は抜け落ちている。介護保険制度と障がい者サービスの違いは根本から理念の違いとしてあることを無視して移行が語られている現実がある。介護保険制度に高齢者の権利規定があるのか、高齢者どこでどのように生活するのは権利として認められているか。等を考えた場合、貴方の介護度は××だからサービス利用はこれだけですよ。これ以上は自己負担ですよ。だめなら施設に入りましょう。障害者サービスとの矛盾が存在する。障害者権利条約では障害者がどこで、だれと暮らすかは権利としている。障害者基本法も権利条約を土台として成立し、障害者総合支援法も成り立っている。
制度自身が根本的に違っている。その矛盾を介護保険のケアマネや現場に押し付けている。現場のケアマネは疲弊して減少をしている。しかも介護報酬を増やすたびに加算の1割は利用者に跳ね返る。益々利用を減らすしかなくなる。介護保険の利用を減らすことが国の習いか。この矛盾を含めてどう立ち向かっていくのか。
令和7年2月 困ったさんの爺さん